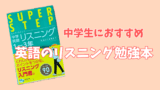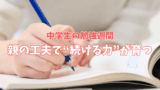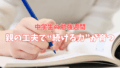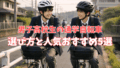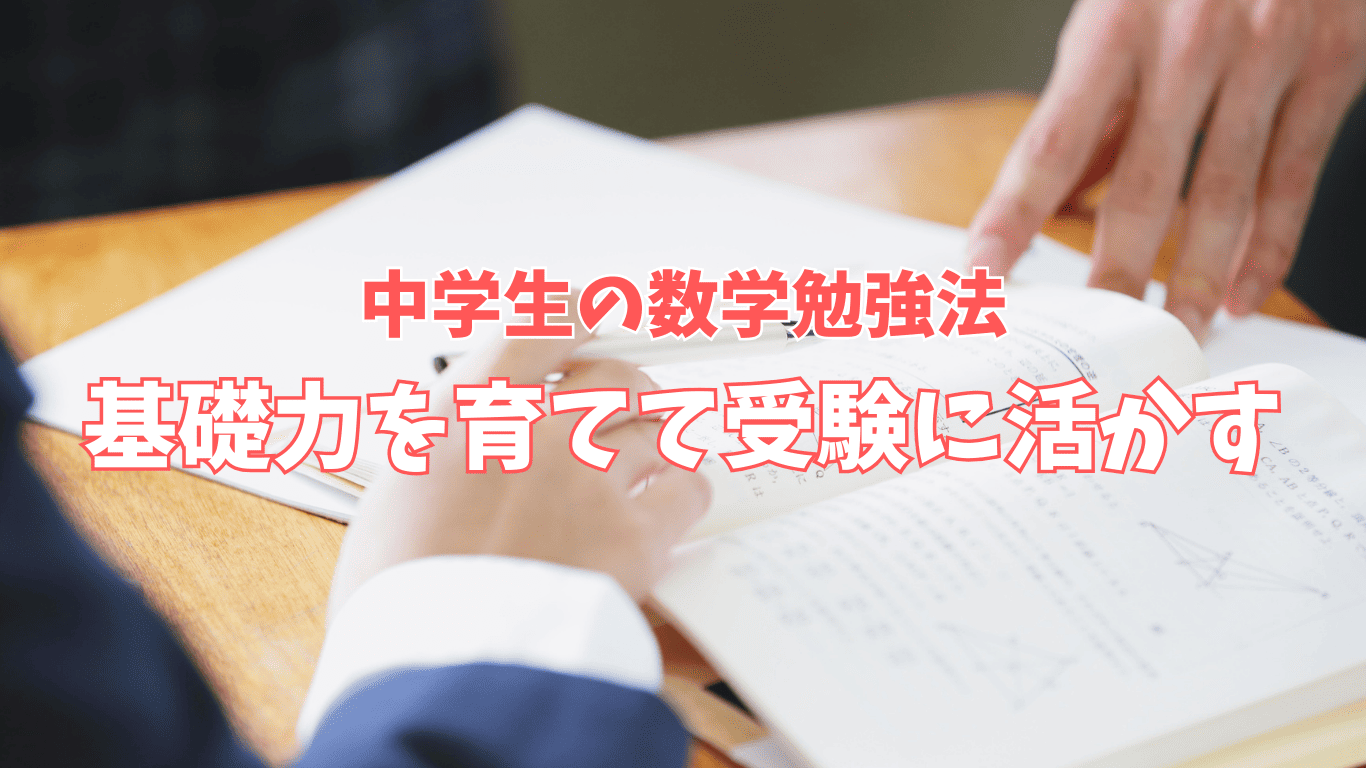
※本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。
「定期テストではそこそこ点が取れるのに、模試や受験問題になると解けない」
「計算はできるけど、応用問題になると手が止まってしまう」
中学生の数学では、こんな悩みを抱える子どもがとても多いです。
私自身も長男のときに同じ経験をしました。
塾に通わせていたので安心していたのですが、実際には基礎力が不十分で、受験に必要な応用力には結びついていなかったのです。
一方で、下の子には「基礎力を日々の勉強習慣に取り入れること」を意識しました。
その結果、テスト前に慌てることもなく、受験に必要な実力を少しずつ積み上げることができました。
「中学生の数学勉強法」を親子で前向きに取り入れるヒント にしていただければ嬉しいです。
我が子の実体験から見えた「数学が伸びない理由」
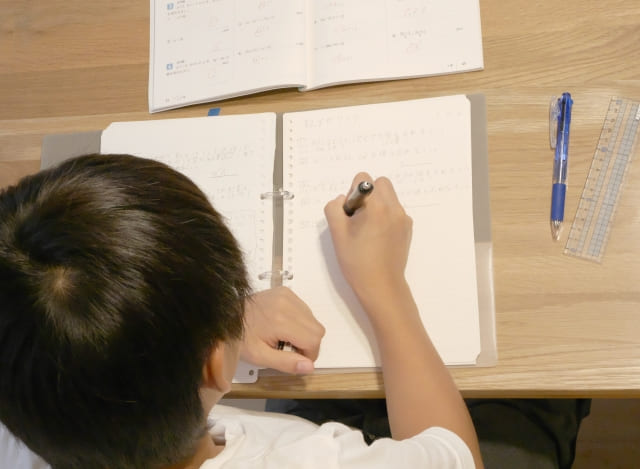
中学生の数学は「計算ができれば大丈夫」と思われがちです。
私も長男のときはそう考えて、塾に通わせていれば安心だろうと油断していました。
ところが現実は違いました。
確かに定期テストでは平均点以上を取れていたのですが、模試や入試問題になると点数が伸びない。
理由を探っていくと、いくつかの共通点が見えてきました。
定期テスト対応だけで終わっていた
学校の定期テストは、範囲が決まっているので「公式を暗記して、その単元だけ解ければ点が取れる」仕組みになっています。
長男もそのやり方でなんとか点は取れていました。
しかし範囲の垣根を超える総合問題になると、公式をどう組み合わせればよいか分からず、手が止まってしまうのです。
答え合わせで終わり、解き方を振り返らない
長男は問題を間違えると、解答を見て「なるほど」と一瞬で終わらせていました。
でも実際には「なぜそう解くのか」「次に同じ問題が出たら自分でできるのか」を確認していなかったのです。
そのため、基礎が身につかず、応用にもつながりませんでした。
基礎力が積み上がっていない
計算や公式の基礎が中途半端なまま、難しい応用問題に挑戦しても解けるはずがありません。
長男の場合、計算のケアレスミスや公式の使い方の理解不足がそのまま残り、高校受験を前に大きな壁となりました。
下の子で意識したこと
長男の経験を踏まえて、下の子では「基礎を毎日の勉強習慣に組み込む」ことを徹底しました。
- 定期テスト対策だけで終わらず、総合問題にも触れる
- 答え合わせは「解き方のプロセス」まで振り返る
- 毎日の計算練習でケアレスミスを減らす
この違いが、同じ「勉強している」でも結果の差につながったのです。
なぜ中学生に数学の基礎力が必要なのか
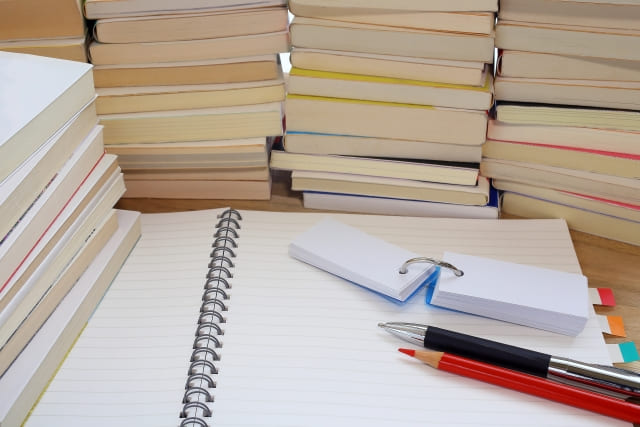
中学生の数学は、「基礎力をどれだけしっかり積み上げられるか」でその後の伸びが決まります。
計算や公式をただ覚えるだけではなく、「どう使うのか」を理解していないと、応用問題や受験問題に対応できないのです。
定期テストと受験問題は別物
学校の定期テストは、範囲が決まっているので「覚えた公式を使えば解ける」問題が多く出ます。
しかし受験では、複数の単元を組み合わせた総合問題が出題されます。
長男のときも、定期テストでは点数が取れていたのに、模試になると得点が急に下がりました。
その理由は「基礎を組み合わせて使う力」が不足していたからです。
基礎力は応用力の土台
応用問題が解けるようになるには、まず基礎の公式や考え方を確実に身につける必要があります。
- 計算力
- 公式を使いこなす力
- 基本的な問題の解き方
これらができて初めて、複雑な問題にも対応できるのです。
高校受験で差がつく科目
数学は高校受験でも特に差がつきやすい科目です。
同じ点数帯の子が集まる入試で、数学の基礎力が不足していると一気に不利になります。
逆に言えば、基礎をしっかり固めておけば「数学で点を落とさない子」になれる。
これは受験全体の合否にも直結します。
親として気づいたこと
長男の経験から、「基礎はできているつもり」では全く足りないと痛感しました。
一方で下の子では、基礎を毎日の学習に組み込むことで、模試や実力テストでも安定して点数を取れるようになりました。
数学の基礎力は、単なる計算練習ではなく、受験を乗り越えるための武器 なのです。
我が家で実践した数学の基礎を固める勉強法
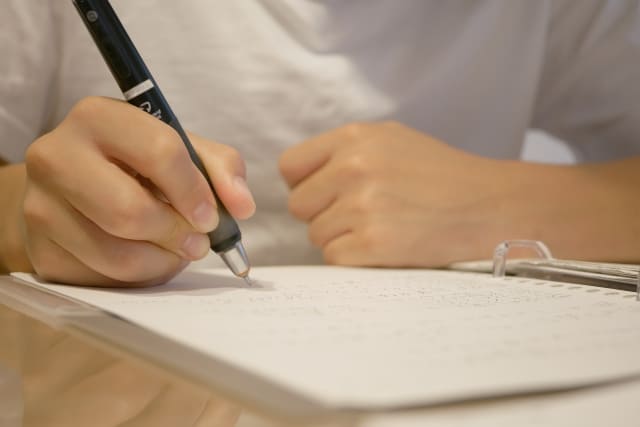
長男のときは「勉強しろ」と言っても、机に座るだけで終わってしまうことが多く、答え合わせもただ赤ペンで丸つけをするだけ。
基礎力が定着せず、応用問題には全く対応できませんでした。
そこで下の子では、次のような工夫を取り入れました。
間違い直しを徹底する
問題を間違えたときに「答えを見て終わり」にせず、なぜ間違えたのかを一緒に確認するようにしました。
- 公式の使い方を間違えたのか
- 計算の途中でつまずいたのか
- 問題文の読み取りを誤ったのか
こうして「自分の弱点」を理解させることで、同じミスを繰り返さなくなりました。
計算練習は短時間でも反復を意識する
中学生には英語や理科、社会など他の教科もあるため、数学を毎日必ず勉強するのは現実的に難しいこともあります。
そこで我が家では、苦手なところ・分からないところを中心に反復して行うことを意識しました。
「分かるまで繰り返す」ことが大切で、同じ問題を何度も解くことで、
- 問題形式に慣れる
- 公式の使い方に慣れる
- 自分の弱点をつぶせる
という効果がありました
また、私はたまに「数学難しい?」「どこでつまずいた?」と声をかけて、子どもの状況を把握するようにしました。
一緒に問題を解いてみると、ただの計算ミスなのか、公式の理解不足なのかが見えてきます。
こうして“苦手をそのままにしない”工夫を続けることで、少しずつ数学への抵抗感が減っていったのです。
公式を“覚える”から“使う”へ
長男は公式を暗記しても「どう使えばいいか」が分からず、応用問題に対応できませんでした。
そこで下の子には、公式を覚えたら必ず「使う練習」をさせました。
例:二次方程式の公式を覚えたら、その日のうちに例題を解いてみる。
「暗記」から「活用」へ変えたことで、基礎力が本当に身につくようになりました。
実感したこと
長男のときは「とにかく問題を解かせれば伸びる」と思っていました。
でも、下の子では「間違い直し」「毎日の積み重ね」「公式を使う練習」という基礎を固める工夫を取り入れたことで、数学に自信が持てるようになったのです。
応用問題につながる工夫
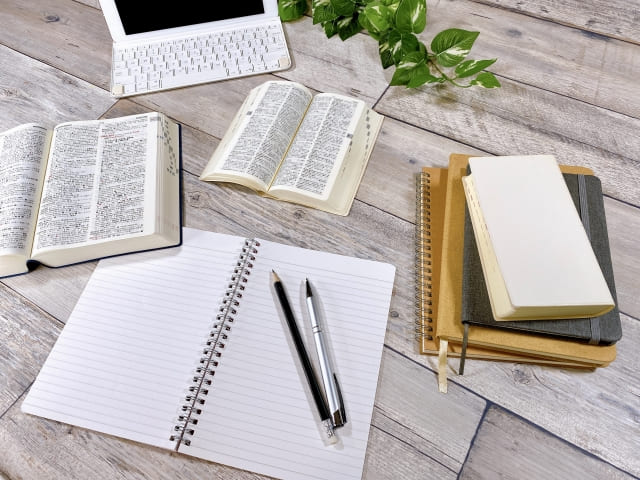
長男も定期テストでは「この範囲ならこの公式を使う」と決め打ちで解けていました。
しかし模試や受験問題になると「どの公式を使えばいいのか分からない」と手が止まってしまったのです。
特に、三平方の定理や円周角、相似の図形など、複数の定理を組み合わせて解く問題になると途端に解けなくなり、実力テストや模試で大きく点を落としていました。
一つひとつの単元は理解していても、それを横断的に使う力が育っていなかったのです。
総合問題に早めに挑戦する
下の子ではこの失敗を踏まえ、基礎が固まった段階で模試や過去問といった総合問題に早めに取り組ませました。
最初は難しく感じても、「どの定理を組み合わせればいいのか」を考える練習になり、少しずつ応用力がついていきました。
間違えた問題は“考え方”を振り返る
応用問題で間違えたときは、答えを写して終わりにせず、
- どの公式を思い浮かべたのか
- 途中で何につまずいたのか
を一緒に振り返りました。
こうすることで「次に同じタイプの問題が出たら解ける」状態に近づけることができました。
一緒に取り組み、過程を褒める
私はときどき子どもの隣に座り、一緒に問題を解いてみました。
そのうえで「ここまでできたならあと少しだね」「前は分からなかったのに、今回は進められたね」と過程を褒めるようにしました。
結果だけでなく、取り組む姿勢や考え方を認めることで、子ども自身も「次はできるようになりたい」と前向きに学ぶようになりました。
基礎力を土台に、総合問題へ早めに挑戦し、間違いを振り返りながら伸ばしていく。
この流れが、応用力を育てるために効果的だったと感じています。
数学検定を受けてみる
我が子の場合、試験に慣れる目的で 数学検定(数検) を受けさせました。
英検や漢検はよく知られていますが、数検は「計算の基礎」から「応用力」まで段階的に実力を測れる検定です。
実際に子どもは「数検で○級に合格した!」という体験がモチベーションになり、普段の勉強にも前向きになれたのです。
こうして「模試や過去問」+「数検」という二本立てで挑戦する機会を増やしたことで、応用力が伸びやすい環境をつくることができました。
家庭でできるサポートの工夫

長男のときは、最初は模試やテストの結果ばかりに目がいって叱ってしまうことも多かったのですが、途中からは接し方を変える工夫を始めました。
一緒に問題を解いてみたり、解き方を口に出させて確認したりすることで、子ども自身も「どこまで理解できているのか」「どうやって解いたらいいのか」を振り返るようになったのです。
その結果、長男も少しずつ答えだけでなく解き方の過程を意識するようになり、振り返りの習慣がついていきました。
この経験が、下の子へのサポートにも大きく生かされています。
リビング学習で自然に見守る
我が家では基本的にリビングで勉強をさせていました。
子どもが集中できるか心配でしたが、親の目が届く環境にすることで、
- 分からないところをすぐ聞ける
- だらけずに取り組める
という安心感がありました。
ただ「勉強してる?」と詰めるのではなく、「どんな問題やってるの?」「難しいところある?」と自然な声かけを心がけました。
結果ではなく過程を褒める
模試やテストの点数だけを見ると叱りたくなってしまいますが、下の子では過程を見ることを意識しました。
- 「前より計算がスムーズになったね」
- 「ここまでは自力でできてるよ」
と声をかけると、子どもも「次はもっと頑張ろう」と前向きになれます。
一緒に考える姿勢を見せる
親が隣に座り、一緒に問題を解いたり解説を確認したりするだけでも、子どもは「自分だけじゃない」と感じられます。
また、親が一緒に取り組むと「どこでつまずいているのか」が分かりやすく、的確にサポートできるようになります。
日常の声かけでハードルを下げる
「ちょっと休憩する?」「1時間くらい経ったよ」など、生活の中で自然に声をかけるだけでも十分サポートになります。
“勉強しなさい”と命令するのではなく、“勉強を続けやすい雰囲気をつくる”ことが大事だと感じました。
忙しくても“寄り添う姿勢”を見せる
私自身、長男のときは仕事で日中はほとんど家におらず、一緒に机に向かう時間なんてありませんでした。
そのため、中3の秋になっても成績が伸びず、つい一方的に怒ってしまうこともありました。
しかしそこからは「今やっている勉強法はどう?」「どこが分からない?」と聞くようにし、解決策を一緒に探すようにしました。
さらに、長男には「この高校に行きたい」という目標があり、それを応援したかったので休みの日や塾に行かない夜は隣に座り、一緒に数学の問題を解くようにしました。
職場にも過去問を持っていき、「どう説明したら分かりやすいか」を隙間時間に考えたりもしました。
その結果、模試の点数自体は劇的には上がりませんでしたが、子どもは「問題を解こう」という努力を見せるようになり、私も「ここまでは正解してるね」「ここでミスしただけだね」と過程を評価して寄り添えるようになりました。
最終的に、長男は第一志望校の入試で数学の過去最高得点を取り、無事合格を果たしました。
これは「親が結果ではなく過程を見て、一緒に考える姿勢を持つこと」が、どれだけ大切かを実感した出来事でした。
実際に使って役立った数学教材中学生におすすめの数学教材
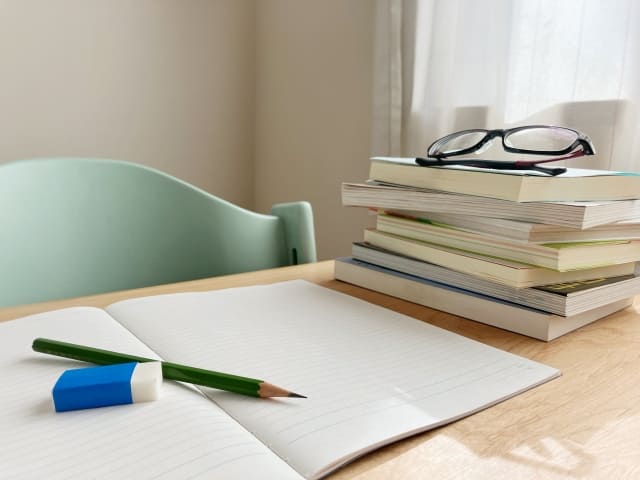
数学の教材は数多くありますが、親として大切にしたいのは「基礎から応用、そして受験へとつながる流れを作れるかどうか」です。
ここでは口コミや評価をもとに調べた、信頼できる教材を3冊紹介します。
それぞれ「どんな子に合うか」もあわせてまとめました。
中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本

数学は積み重ねの教科なので、「1年生の内容があやふやなまま3年生に進んでつまずく」というケースが多いです。
我が家の長男も同じで、受験前に基礎の穴が大きな壁となりました。
そんなときに便利なのが 『中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本』。
15万部を突破したロングセラーで、2021年度の新学習指導要領にも対応しています。
基礎を一気に整理して、数学を“分かる”に変えたい子には、この1冊がとても便利です。
詳しくはこちらからチェックできます👇
わかるをつくる 中学数学 新装版

中学数学は、定期テスト対策だけでなく、受験に直結する「応用力」を育てることが欠かせません。
『 わかるをつくる 中学数学 新装版』 は、基礎から入試レベルまでを3年間通して学べるハイレベル参考書です。
新学習指導要領にも対応し、学校の授業・日常学習・定期テスト・入試対策まで幅広く使える一冊です。
基礎から応用まで「これ1冊」で通せる安心感が欲しい方には特におすすめです。
詳しくはこちらからチェックできます👇
高校入試「解き方」が身につく問題集 数学

公立高校入試の数学は、ただの暗記では解けない「考える力」を必要とする問題が数多く出題されます。
本書は、そうした「出題頻度が高く」「解き方にコツがある」問題に的を絞り、効率的に得点アップを目指せる問題集です。
「暗記では太刀打ちできない問題の“解き方”を反復で定着させたい」受験生に。
詳しくはこちらからチェックできます👇
中学生の通学勉強法でよくある質問(FAQ)
毎日どのくらい数学を勉強させるのが良いですか?
他の教科もあるので、毎日長時間やる必要はありません。
短時間(10〜20分)でも良いので、計算練習や苦手分野の反復を続けることが効果的です。大事なのは「やらない日を作らない」よりも「苦手を放置しない」ことです。定期テストの勉強と受験対策はどう違うのですか?
定期テストは範囲が決まっているため「暗記や単元の理解」で対応できます。
しかし受験では、複数の単元を組み合わせて解く総合問題が多く出題されます。
定期テストの勉強だけでは不十分なので、早めに模試や総合問題に取り組むことが大切です。数学が苦手な子に、いきなり問題集をやらせても大丈夫ですか?
苦手意識が強い場合は、基礎を整理する参考書から始めるのがおすすめです。
いきなり難しい問題に取り組むと挫折しやすいので、まずは「1冊で中学3年分を総復習できる教材」などを活用して、理解の抜けをなくすことから始めましょう。親はどこまで勉強に関わるべきですか?
つきっきりで教える必要はありませんが、子どもの勉強を見守り、声をかけることが大事です。
「どこまで解けた?」「ここまでは理解できているね」など過程を認めてあげると、子どもが前向きに取り組めるようになります。模試や過去問はいつから取り組めばいいですか?
中3の夏以降が目安ですが、基礎がある程度固まった段階で早めに挑戦するのがおすすめです。
初めは解けなくても、「どの公式を使うのか」を考える練習になるので、応用力を育てるステップになります。数学検定(数検)は受けさせた方がいいですか?
数検は試験に慣れる良い機会になります。
合格すると子どもの自信につながり、「次はもっと頑張ろう」というモチベーションアップ効果も期待できます。
ただし無理に受ける必要はなく、子どもの性格や目標に合わせて検討すればOKです。
まとめ|基礎力を育てることが受験突破の第一歩

中学生の数学は「基礎力」がなければ先へ進めません。
我が子の経験からも、計算や公式の使い方をしっかり定着させていないと、応用問題や入試問題に太刀打ちできないことを痛感しました。
だからこそ中学生の数学勉強法では、まず「基礎を固める」ことを第一に考える必要があります。
短時間でも計算練習を積み重ね、苦手な単元を繰り返し練習すること。
その上で、模試や過去問、応用問題に挑戦し、「どの公式をどう使うのか」を自分で考える練習をしていくことが、受験突破の大きな力になります。
また、家庭でできるサポートも重要です。
結果だけを見て叱るのではなく、勉強の過程を一緒に見守り、できた部分を認めてあげることで、子どもは前向きに数学に取り組むようになります。
基礎力を育てることこそが、受験突破の第一歩。
毎日の小さな工夫と継続が、未来の大きな成果につながっていきます。