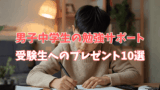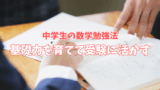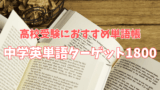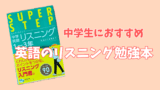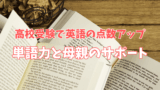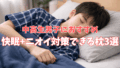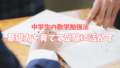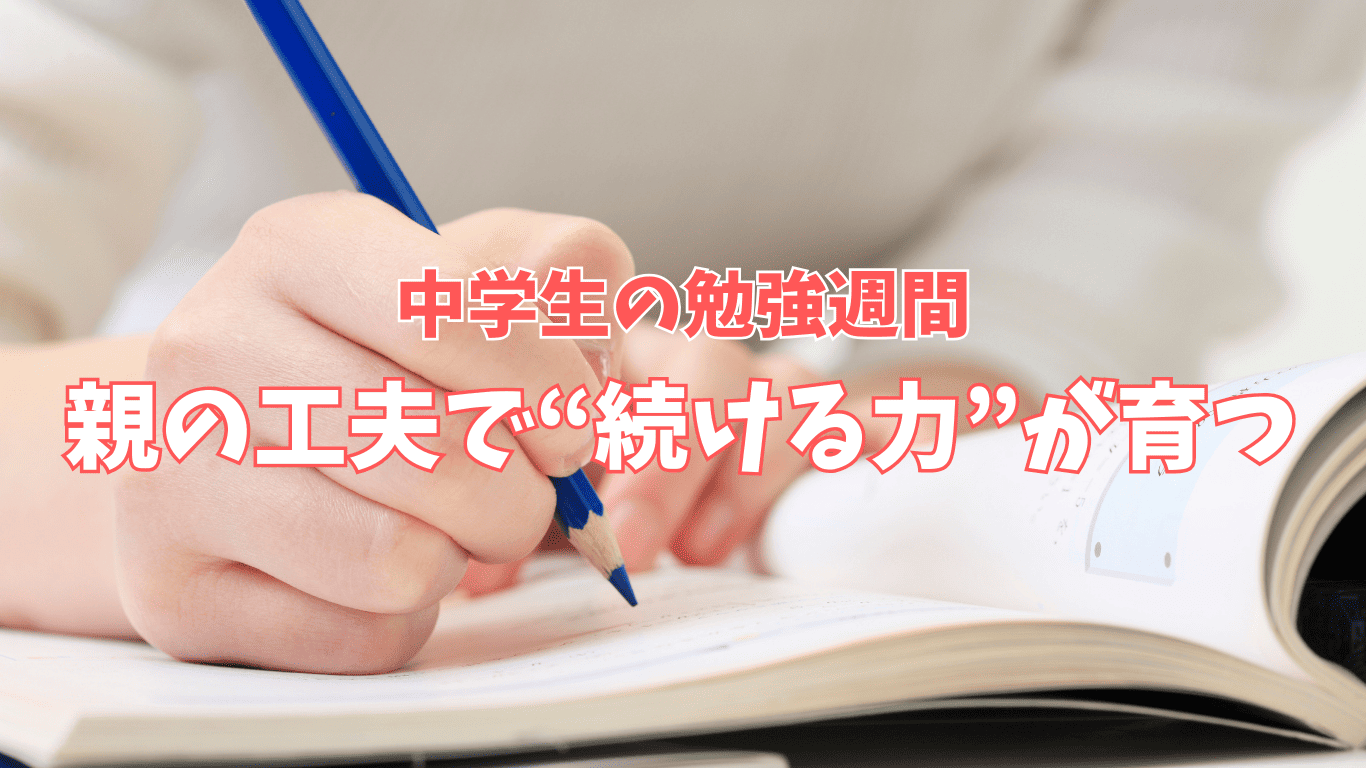
「中学生になったのに全然勉強しない…」「ゲームやスマホばかりで机に向かわない」
こうした悩みは、多くの家庭で共通しているのではないでしょうか。
特に思春期・反抗期の男子は、親が「勉強しなさい」と言えば言うほど反発してしまい、勉強習慣をつけるのは簡単なことではありません。
私自身も、上の子のときはがむしゃらに「宿題やった?」「テスト勉強は?」と声をかけ続け、結果的に親子関係がぎくしゃくしてしまった苦い経験があります。
しかしその反省から、下の子には「毎日コツコツ取り組める環境を家庭で整えること」に意識を変えました。
すると、勉強ゼロだった息子も、今では机に座るのが当たり前になり、無理なく勉強習慣を身につけられるようになったのです。
塾に行かなくても家庭でできる工夫はたくさんあります。
この記事を通じて「勉強習慣は特別なものではなく、毎日の小さな積み重ねでつけられる」ということを実感していただければ嬉しいです。
※本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。
\👀受験生の男子中学生に送るプレゼントが気になる方はこちらもチェック/
勉強習慣ゼロだった息子の中学生活
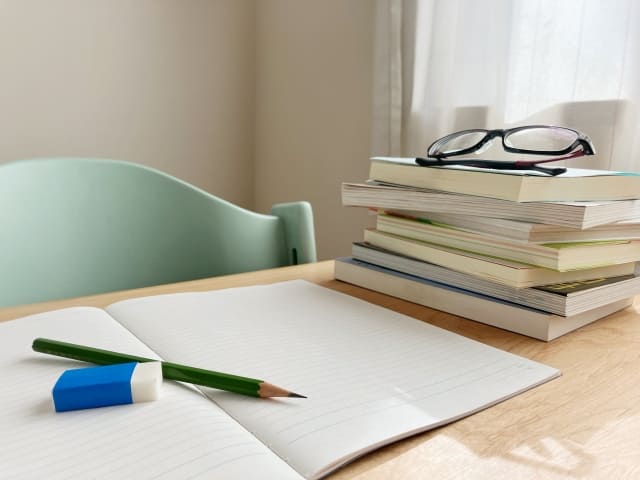
長男は中学に入ると同時に塾に通わせていたので、私は正直「勉強面は大丈夫だろう」と安心していました。
実際、テストの点数はそこそこ取れていたのですが、ふたを開けてみると内申点はあまり良くなかったのです。
理由は単純で、学校生活の勉強習慣がほとんど身についていなかったからでした。
宿題を出したり出さなかったり、提出物もきちんと出せない。
塾では問題を解いているのに、家庭や学校では勉強習慣がないため、先生からの評価は低いまま…。
私もだんだん「提出物を出しなさい」「宿題をやりなさい」と口うるさく言うようになりました。
返事だけは「うん」とするものの、いざ机に向かってもただ座っているだけ。
ノートを開いても、鉛筆が動いていないこともありました。
結局、中学3年生になるまで「宿題をきちんと出す」という当たり前の習慣さえ定着しなかったのです。
塾に通っていても勉強習慣がつかない理由
私の長男だけの問題かと思っていましたが、同じように「塾には通っているのに家庭で勉強習慣がつかない」という悩みを抱える家庭は少なくないようです。
塾頼みの落とし穴
塾では点数アップのための知識は得られるが、「宿題を計画的に出す」「毎日机に向かう」といった生活習慣は家庭でしか育たない。
内申点の重要性
公立高校入試では、テストの点数だけでなく内申点が重視される地域が多い。
提出物や授業態度が評価に大きく影響する。
形だけの勉強時間
勉強時間=机に座っている時間、ではない。
本当に手を動かし、理解して、継続してこそ学習習慣になる。
つまり塾に通っていても、家庭での習慣が伴わなければ学習効果は限定的なのです。
私が学んだこと
この経験から、「塾に行っているから安心」という考えは危険だと痛感しました。
勉強習慣が家庭や学校生活に根づいていないと、テストで点数を取れても内申点が伸びず、進路に影響してしまいます。
そして何より、「勉強するのは誰のためか」 という意識を子ども自身が持たない限り、親がいくら口うるさくしても身にならないのです。
なぜ中学生は勉強習慣をつけにくいのか?
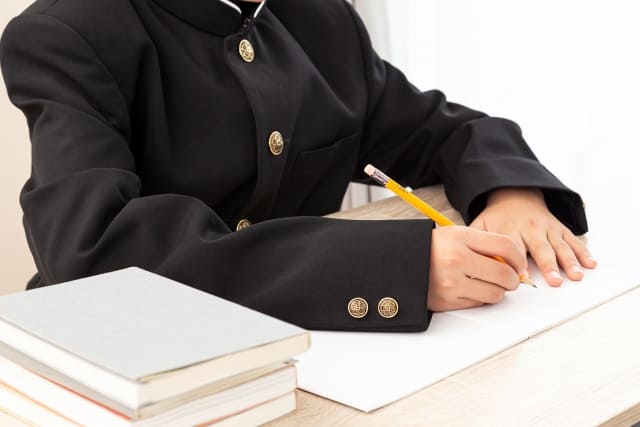
私自身、長男を見ていて「なぜこんなに勉強の習慣がつかないのだろう?」と何度も疑問に思いました。
小学生の頃は宿題をこなしていたのに、中学に入った途端に机に向かわなくなった。
親が「勉強しなさい」と言うと返事はするけれど、ノートは真っ白。
こうした姿に不安と苛立ちを覚えながら、原因を探るようになりました。
調べていく中で、そして実際に我が子を観察していく中で、中学生が勉強習慣をつけにくい背景には以下の要因があると分かりました。
思春期特有の自立心と反抗心
中学生になると、親が「勉強しなさい」と言うだけで反発することが増えます。長男も返事はするけれど、結局は机に向かわないことが多くありました。
これは怠けではなく、第二反抗期に見られる自立心の芽生えです。
10〜12歳頃から始まり、小学校高学年〜高校生にかけて続くこの時期は、子どもが保護者の言うことに反発しながら、精神的に自立し、自我を確立していく大切なプロセスとされています(LITALICO ジュニア)。
報酬がすぐに見えない勉強の性質
勉強は「やったらすぐ成果が出る」ものではありません。
テストや通知表に反映されるのは数週間から数か月先。
一方、ゲームやスマホは「今すぐ楽しい」「達成感がある」活動なので、子どもはそちらに流れがちです。
長男も、問題集よりゲームに時間を費やす方が圧倒的に多く、習慣化が難しいのは当然だと感じました。
中学生活の環境変化
小学校に比べて、中学は部活動や友人関係が一気に広がります。
部活で帰宅が遅くなり、宿題をやる時間が削られたり、友達とのコミュニケーションに時間を使ったり…。
その中で「毎日机に向かう」という習慣を後回しにしてしまう子は少なくありません。
「勉強時間=机に座っている時間」という誤解
私の長男もそうでしたが、勉強しているフリをして、ただ机に座っているだけということがよくありました。
つまり「机に向かう=勉強している」と思い込んでいて、実際には手も頭も動いていない。
習慣化とは「形を整えること」ではなく「中身を積み重ねること」だと痛感しました。
親として学んだこと
こうした要因を踏まえると、「中学生に勉強習慣をつける」のは親が思う以上にハードルが高いことが分かります。
そして、ガミガミ言っても逆効果であることも実感しました。
むしろ「小さな行動を習慣にする仕組み」を整え、子どもが自分の意思で動ける環境をつくることが大切だと考えるようになったのです。
勉強習慣を身につけることが中学生に必要な理由

私の長男を見て痛感したのは、「勉強はテスト前だけやっても成果につながらない」 ということです。
塾に行って点数はそこそこ取れていても、家庭学習の習慣がなかったため、提出物や授業態度が評価されず、内申点は伸びませんでした。
高校受験で内申点が重視される
多くの公立高校入試では、テストの点数だけでなく内申点(通知表)が合否に大きく関わります。
内申点には授業態度や提出物が含まれるため、毎日の積み重ねが欠かせません。
「やれば点数は取れるけど、日常の勉強習慣がない」という状態は、進学に直結するリスクになります。
「勉強はやるのが当たり前」にする
習慣がついていない子は、毎回「今日は勉強するかどうか」を意思で決める必要があります。
一方、習慣がある子は「歯磨きと同じ」で迷わず取り組める。
この違いが、中学生の3年間で大きな差になっていきます。
部活や友人関係との両立がしやすくなる
中学生は勉強以外にも部活や交友関係で忙しくなります。
だからこそ、短時間でも毎日机に向かう習慣があれば、生活リズムを崩さずに勉強と両立できるのです。
親として実感したこと
長男のときに「習慣づけの大切さ」を軽視した結果、後から苦労しました。
下の子では「まず毎日10分でも机に向かう」ことから始めたところ、自然と勉強が生活の一部になり、テスト前に慌てることも減りました。
我が家で実践した「勉強習慣づけ」の工夫
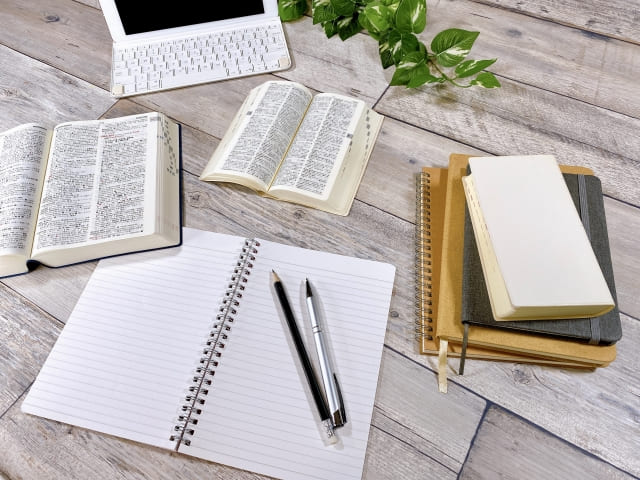
長男のときに「勉強しなさい」と口うるさく言っても習慣は身につかず、結局うまくいきませんでした。
そこで下の子には「叱る」ではなく「仕組みづくり」で習慣化をサポートするようにしました。
具体的には、次のような工夫です。
勉強時間は短く、最初は10分から
最初から「1時間やりなさい」と言っても続きません。
我が家では「まずは10分だけ」とハードルを下げてスタートしました。
短時間でも毎日続けることで「机に向かうのが当たり前」という感覚が少しずつ身につきました。

習慣化の研究でも「無理に大きな行動を設定せず、まずは『ちょっとだけ』から始めることが大切」とされています。
さらに、行動はスタートから約3週間で日常生活に組み込まれやすいという報告もあり、実際に10分勉強を続けるうちに抵抗感が減っていきました(ダイヤモンド・オンライン)。
毎日同じ時間に机に向かう
夕食後の19:30〜20:00を「勉強タイム」と決めました。
毎日同じ時間に取り組むことで、子どもも迷わず動けるようになり、親も声かけがしやすくなりました。
親も一緒に机に座る(できる範囲でOK)
理想は、子どもが勉強する時間に親も横で本を読んだり仕事をしたりすることです。
「一緒に机に向かっている」という雰囲気があると、子どもも自然と集中しやすくなります。
ただし、家事や下の子の世話で難しい家庭も多いですよね。
そんなときは、「リビング学習」のように子どもが勉強しているそばで親が洗い物やアイロンがけをしていても大丈夫。
大切なのは、「同じ時間に、親も何かに取り組んでいる」空気をつくることです。

完璧に一緒に座らなくても、「家族が一緒に頑張っている時間」という雰囲気を見せるだけで、子どもは安心して習慣を続けられます。
成果ではなく「やったこと」を認める
長男のときは「点数」で褒めていましたが、下の子には「いつも通り勉強した」「できなかった問題ができるようになった」という行動自体を認めるようにしました。
小さな成功体験を積み重ねることで、「やればできる」という自信が芽生えていきます。
「やることをやったらあとは自由時間」と声かけする
下の子には、勉強を「義務」ではなく「区切りのある活動」として意識させるようにしました。
「宿題と10分の復習が終わったら、あとは自由時間でいいよ」と伝えると、子どもはゴールが見えるので取り組みやすくなります。
長男のときは「もっと勉強しなさい」と終わりを曖昧にしてしまい、かえって反発を招いていました。
下の子では「やることをやれば自由に過ごせる」というメリハリを意識させることで、勉強と遊びの切り替えがスムーズになり、習慣として定着しやすくなったのです。

「やることをやったら自由時間」というシンプルなルールが、子どもにとって大きな安心感になり、毎日の勉強を続けるきっかけになりました。
実感したこと
こうした工夫を重ねた結果、下の子は「勉強するかどうか」ではなく「いつ勉強するか」を考えるようになり、自然と机に向かう習慣が身についてきました。
習慣は努力ではなく仕組みでつくる――これが、私が実際に体験して学んだ一番の教訓です。
科目別の小さな工夫

勉強習慣をつけるときは「全部を一度に完璧にやろう」とするのではなく、科目ごとに“これだけは”という小さな工夫を決めて続けるのがポイントです。
我が家でも「たったこれだけ」を意識したことで、下の子は無理なく毎日の学習を習慣にできました。
国語:毎日の小さな積み重ねを習慣に
下の子は特に国語が苦手でした。
でも、国語力がないと数学や理科の文章問題を読む力にも影響することは分かっていたので、「どうにかしなければ」と思いつつ、国語の勉強法がよく分からない時期がありました。
そこで我が家で決めたのは、「本を読む」か「漢字を勉強する」ことを毎朝の学校の「朝学」の時間に組み込むこと。
量は少なくても「毎日必ず文章を読むことに触れる」習慣を作ったのです。
さらに中学3年生になってからは、受験生ということもあり、朝学や家庭学習で 1日1題は必ず国語の問題を解く というルールを決めました。
今では国語を避けることなく、毎日の学習に自然に組み込めるようになっています。

国語は成果が出るのに時間がかかる科目ですが、毎日の積み重ねが最も大きな力になる科目でもあります。
数学:解き方を理解する習慣をつける
数学は普段、わからなかった問題を振り返ることを基本にしました。
その際、間違った問題はそのままにせず、必ず解答を見て「どう解くのか」を理解するまで確認します。
多くの子が「答えだけ見て終わり」にしがちですが、それでは力がつきません。
我が家では 解き方を覚えることに重点を置く ようにしました。
基礎問題での積み重ねこそが、中学3年生になってからの受験対策=応用問題につながると実感しています。
実際、上の子のときは基礎の理解があやふやなまま中学3年の秋を迎えました。
模試や入試では全範囲から出題されるため、応用問題になると「何の公式や法則をどのように使えばいいのか分からない」という状態に。
単元ごとの勉強はできても、基礎と基礎を組み合わせて解く力が不足していたのです。
この経験から、ただ答えを出すのではなく「解き方や考え方のプロセスを確認する」ことが何より大切だと痛感しました。
基礎の解き方をしっかりマスターすることが、数学の得点力アップに直結するのです。
英語:単語力をベースに、リスニングを毎日習慣化
英語の学習で一番大切だと感じたのは、やはり 単語力 でした。
我が家では「英語を勉強するときは、まず単語から」と決め、中学2年の夏休みから単語帳を使い始めました。
最初は「声に出して見るだけでもいい」と伝え、毎日単語帳を開く習慣をつけることを意識しました。
「これをやっておくと中3になって楽になるよ〜」と声かけすると、下の子も嫌がらず取り組めました。
上の子での失敗
長男のときは、単語力不足に本人も気づかず、単語帳もなかったため「どう勉強したらいいのか」が分からなかったようです。
学校や塾でプリントはもらっていたものの、習慣化できなかったため、テスト前に一気に暗記してもすぐ忘れる…という繰り返しでした。
下の子での工夫
その反省を踏まえて下の子には、「1ページだけでも見よう」「寝る前にちょっとだけ見よう」と声をかけ、単語を日常のスキマ時間に習慣化しました。
その結果、定着度が大きく変わり、テストでも安定して得点できるようになりました。
リスニング対策も習慣化
もうひとつ課題だったのがリスニングです。
下の子も「聞き取れん…考えよったらどんどん進むから、何言ってるのか分からんくなる」と悩んでいました。
そこで本屋でリスニング教材を購入し、毎日1題だけ聴く習慣をスタート。
繰り返すうちに少しずつ聞き取れるようになり、今ではリスニングで点を落とすことがほとんどなくなりました。
英語は「単語力」と「耳慣れ」がすべての土台。
小さくても毎日の積み重ねが、中3の大きな力になると実感しています。
実際に使った英単語帳やリスニングの本はこちらで紹介しています!
理科・社会:暗記科目こそコツコツの積み重ねが大事
理科や社会は「暗記すれば点が取れる」科目ですが、同時に「一気に詰め込んでもすぐ忘れる」科目でもあります。
だからこそ、コツコツ積み重ねる習慣がとても大事だと実感しています。
自分自身の経験
私自身、中学生の頃に社会のテストで20点台を取り、親も驚いて塾に放り込まれたことがありました。
近所のおばちゃんがやっていた個人塾で、社会は私ひとりのマンツーマン。
毎週「ここまで覚えてきてね」と宿題が出され、強制的に暗記を習慣化させられました。
その結果、テスト週間の1週間で無理に詰め込む必要がなくなり、他の教科の勉強に時間を使えるようになりました。
上の子のケース
上の子は「考える教科(数学や英語の応用)」が苦手でしたが、社会は好きだったため模試でも高得点を取っていました。
好きだから自分から勉強する → 結果的に社会は得意科目に。
受験でも「基礎を固めるべき時期」に社会を先に仕上げてしまったのは、良い意味での強みになったと感じます。
下の子での工夫
下の子には「一夜漬けでは通用しない」と考え、テスト2〜3週間前から暗記スタート。
本番のテスト週間に入る頃には、理科・社会の範囲をすでに2周終えている状態にしました。
中学3年の夏休みは国語・英語・数学を中心にしつつ、気分転換に理科や社会を挟む。
テストが近づいたら本格的に取り組む、というリズムで進めました。
理科や社会は 点が上がりやすいけれど下がりやすい科目。
だからこそ「短期で詰め込む」より「習慣として繰り返す」方が安定した成果につながる。
親が家庭でできるサポートの工夫
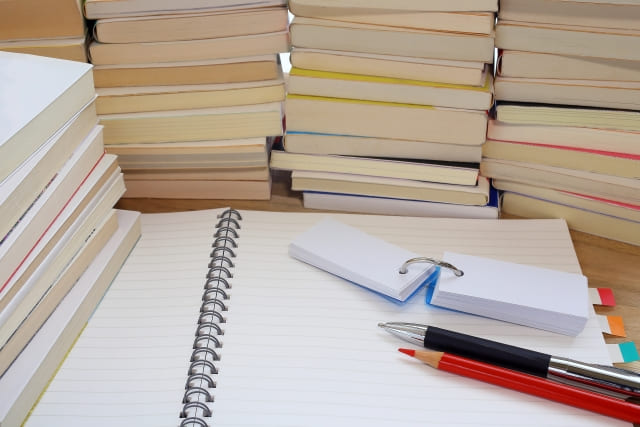
「勉強しなさい」と繰り返すだけでは、子どもはなかなか動きません。
私自身、長男のときにガミガミ言って失敗した経験があるので、下の子には “習慣をつくる環境づくり” を意識しました。
ここでは、親が家庭でできるサポートをまとめます。
ガミガミ言わない
長男のときは「宿題した?」「テスト勉強は?」と毎日のように言い続けました。
しかし結果は、反発が強まり、勉強が嫌なこととして定着してしまいました。

やることをやったら自由時間」というシンプルな声かけに変えることで、下の子は前向きに勉強に取り組めるようになりました。
学習環境を整える(基本はリビング勉強)
我が家では、下の子は基本的に リビングで勉強 しています。
自室にこもるとついスマホや漫画に手が伸びてしまうので、家族の目があるリビングの方が集中できるのです。
勉強道具はリビングの棚にまとめて置き、すぐに取り出せるようにしました。
机の上は「参考書とノートだけ」をルールにし、散らからない工夫もしています。
そして様子を見つつ「どんな問題やってるの?分かる?」「難しいねぇ」「ちょっと休憩する?」「◯分たったよー」など日常の延長にある声掛けをしました。
これにより、子どもに「今は勉強の時間だ!」と身構えさせず、生活の中で自然に机に向かえるようになったのです。
勉強を“特別なこと”ではなく“日常の一部”にする。
この感覚が、習慣づけを無理なく続ける最大のポイントでした。
小さな行動を認める
「100点を取ったら褒める」よりも、「机に座れた」「宿題を提出できた」といった行動をその場で認めることが大切です。
小さな達成感の積み重ねが「やればできる」という自己効力感につながります。
完璧を求めず、続けられる範囲で
勉強習慣は“持久戦”です。
毎日1時間完璧にやらせるのではなく、10分でも続けられたらOKと考える方が親も子もラクになります。
長男のときは「もっとやらせなきゃ」と焦っていましたが、下の子では「短くても毎日続ける」を意識してから、自然に勉強が定着しました。
一緒に取り組む姿勢を見せる
長男のときは、受験期も一人でずっと勉強している状態でした。
しかし点数はなかなか伸びず、模試の結果ばかりを見て「どうしてできないの?」と叱ってしまうことが多かったのです。
そんなある日、職場の人から「今の中学生の数学ってすごく難しいよ」と言われ、実際に息子の模試の問題を見せてもらいました。
本当に難しく、親の私でもちんぷんかんぷん。
そこで初めて「結果だけを見て叱るのは違う」と気づきました。
それからは、点数ではなく“経過”に注目することを意識。
私自身も一緒に数学の問題を解いたり、隣で解答を見ながら考えたりするようにしました。
すると模試の結果が悪くても、
- 「ここ、前にやったやつができてるじゃん」
- 「ここまで分かってるなら、あとは時間があれば解けそうだね」
と具体的に褒められるようになり、長男も「ここまでできたけど、ここから分からなかった」と積極的に振り返るようになりました。
一緒に問題に取り組むことで、子どもの成長過程をしっかり見られる。
そして「結果」ではなく「プロセス」を褒めることで、勉強への前向きな気持ちが育つのだと実感しました。
結果|中学生の息子が毎日コツコツ勉強するようになった変化
長男のときは「宿題やった?」「テスト勉強は?」と口うるさく言っても、机に座るだけで何も進まないことが多く、親子でストレスを抱えていました。
しかし、下の子では 小さな習慣づけと親のサポート を意識したことで、少しずつ確実に変化が表れました。
勉強に向かうハードルが下がった
以前は「勉強=いやなこと」でしたが、「10分だけ」「やることをやったら自由時間」というルールにしたことで、自然と机に向かえるようになりました。
今では「勉強するかどうか」ではなく「どのタイミングでやるか」を自分で考えるようになっています。
テスト前のストレスが減った
長男のときはテスト前に一気に詰め込むスタイルで、私も本人も常にピリピリしていました。
下の子は普段から予習・復習を少しずつ続けていたので、テスト週間に「ゼロからやらなきゃ」という焦りがなくなりました。
結果として、テスト前でも落ち着いて勉強に取り組めています。
自分から振り返るようになった
以前はテストが返ってきても、結果だけを見て落ち込んで終わりでした。
しかし下の子は、定期テストのあとに 自分から解答を見直すように なりました。
「あ、ここ間違えた!」
「ここやったのに〜悔しい!」
「次はこういうの気をつけんといけんね」
と、間違えた箇所を自分の言葉で振り返るようになったのです。
点数に一喜一憂するのではなく、「どうすれば次に活かせるか」を考えられるようになったのは大きな成長でした。
この“振り返りの習慣”こそ、勉強を続ける力の土台になっています。
学習習慣が“日常”になった
何より大きな変化は、勉強が生活の一部になったことです。
「歯磨きと同じで、やらないと気持ち悪い」という感覚になり、親が言わなくても机に向かう日が増えました。
たまに、ゲームに夢中になっている時はありますが、そういう時は大目に見ています。
習慣は一朝一夕ではつきませんが、小さな工夫を続けたことで、確実に成果につながったと感じています。
親として感じたこと
「勉強習慣をつける」というと大変そうに聞こえますが、実際は “小さな積み重ねを生活に溶け込ませること” でした。
長男での失敗があったからこそ、下の子で工夫できたことも多く、「習慣づけは親の工夫次第で変えられる」と実感しています。
中学生の勉強週間についてよくある質問(FAQ)
中学生に勉強習慣をつけるのは、いつから始めるのがいいですか?
できれば 中学1年生の最初から 小さな習慣を作るのがおすすめです。
「1日10分だけ」でもいいので、早めに習慣化するとテスト前に慌てる必要がなくなります。
ただし、途中からでも遅すぎることはありません。中学2年や3年からでも「短時間・毎日」のリズムを作れば定着します。勉強しなさいと言うと反発されてしまいます。どうすればいいですか?
思春期の子どもは「やらされる勉強」を嫌がります。
そのため「勉強しなさい」よりも、
「やること終わったら自由時間だよ」
「今日は10分だけやってみよう」
といった声かけの方が効果的です。
親が 勉強を特別なものにせず、日常の一部にする雰囲気づくり を意識しましょう。塾に通えば勉強習慣は自然につきますか?
塾は知識を教えてくれますが、日々の習慣づけは家庭でしかできません。
塾に通っていても、宿題や提出物が出せない子は内申点で不利になることがあります。
塾はあくまで補助であり、習慣化の土台は家庭で整えることが大切です。どの教科から勉強習慣をつけるのが良いですか?
苦手教科よりも 取り組みやすい教科から始めるのがおすすめです。
「英単語を1日3つ」「漢字を3個」など、小さなステップを積み重ねることで自信がつき、他の教科にも広がっていきます。勉強習慣をつけるのに、どれくらい時間がかかりますか?
一般的には 3週間〜3か月程度で行動が習慣として定着しやすいといわれています。
最初は短時間から始めて、徐々に時間を伸ばすと長続きします。親はどこまで勉強を見てあげればいいのでしょうか?
全部を教える必要はありません。
むしろ「結果だけを見る」のではなく、過程を一緒に振り返ることが大切です。
例えば「ここまではできたね」「次はここを気をつけよう」と声をかけるだけでも、子どもは安心して次につなげられます。
まとめ:中学生の勉強習慣は「小さな工夫」から変えられる

「中学生の勉強習慣」について検索してこの記事にたどり着いた方は、
「うちの子が全然勉強しない」
「どうしたら毎日机に向かってくれるんだろう」
といった悩みを抱えているのではないでしょうか。
私自身も長男のときに失敗を重ね、「勉強しなさい」と叱るだけでは習慣はつかないことを痛感しました。
しかし下の子で工夫を取り入れたことで、少しずつ「勉強は特別なことではなく、生活の一部」という習慣に変わっていきました。
大事なのは、最初から完璧を目指さないこと。
- 勉強時間は「10分だけ」から始める
- 「やることをやったら自由時間」と区切りをつける
- 間違えても「次はここを気をつけよう」とプロセスを褒める
こうした小さな工夫を積み重ねることで、子どもは自然と毎日机に向かうようになります。
中学生の勉強習慣は、親のちょっとした工夫と声かけ次第で必ず変えられます。
今日からできることを一つずつ取り入れて、子どもの「続ける力」を育てていきましょう。